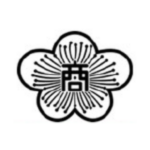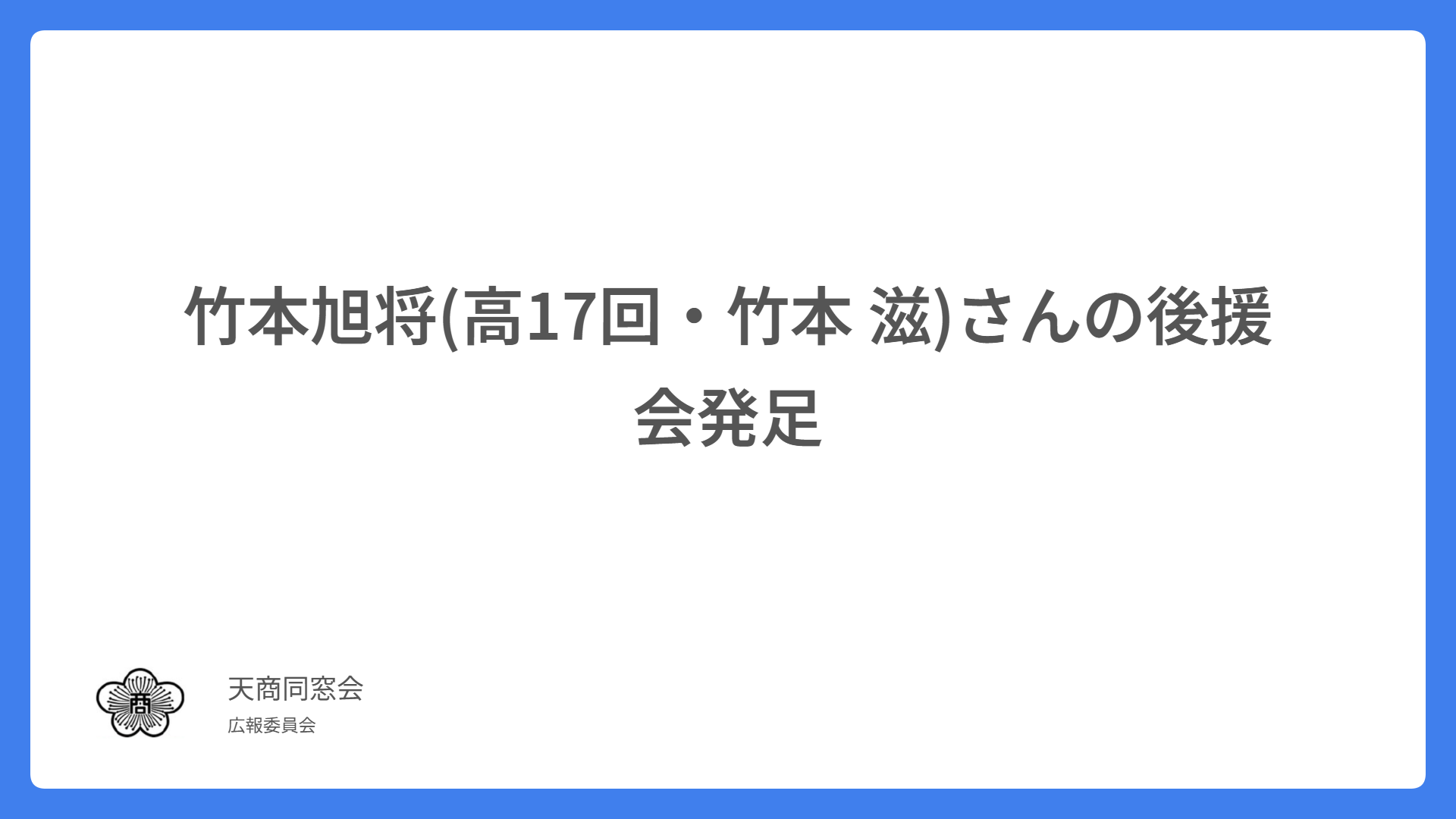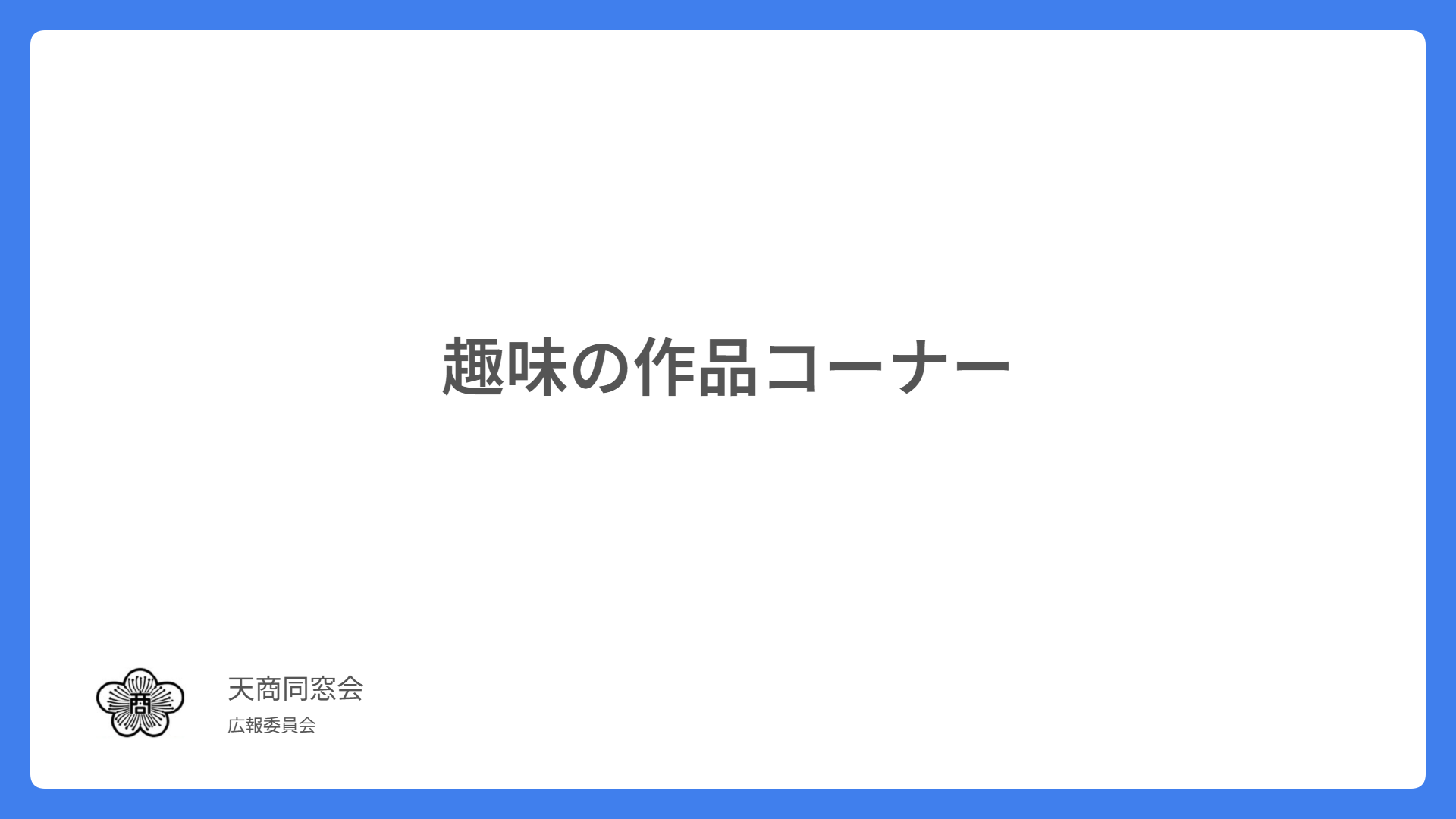中央公会堂を寄付した人物は天商生の大先輩だった=岩本栄之助と中之島・中央公会堂=
今年の同窓会総会・懇親会は、昨年と同様に中之島の中央公会堂で開催されます。公会堂は個人の寄付により建設され、寄付者の岩本栄之助は天商のルーツの商業学校の卒業で、私たち天商卒業生の大先輩ともいえる人物です。
そこで岩本栄之助と公会堂について、紹介を兼ねてまとめてみました。
『義侠の相場師』と呼ばれた栄之助
☆家業の両替商「銭屋」を継ぐまで

岩本栄之助は、明治10 (1877) 年、大阪市南区(現在の中央区南船場付近)にあった両替商「銭屋 ( のちに岩本商店に改称 )」 の次男として生をうけた。小学校卒業後、天商のルーツにあたる大阪市立大阪商業学校に進学。大阪清語学校・明星外国語学校にも通い、商業学と外国語を学びながら家業を手伝っていた。
30才で徴兵令により召集され、日露戦争にも従軍。奉天大会戦など大陸を転戦するなかで満州軍総参謀長・児玉源太郎の副官も務めている。除隊後、家業を継ぐ予定だった長男が死去したため代わって銭屋を継ぎ、大阪株式取引所の仲買人に登録された。
☆「義侠の相場師」の誕生
岩本仲買店と名称を改めていた栄之助は、南満州鉄道株をはじめとして「成り金」という流行語が生まれるほど熱狂する相場にも冷静に対処。礼儀正しい学者肌で、相場師のイメージとは程遠かった。
日露戦争後の暴騰相場にあって、岩本家が大株主となっていた大阪株式取引所の株が急騰すると、東京の兜町筋が買い方に回り、大阪の北浜筋は「いずれ下がる」と見て売り方で対抗。しかし暴騰は続き、損失した側が出す追い証(追加の保証金)も多額となって、大阪側は半数以上が破産の危機に陥る。栄之助は堅実に買い方に回っていたが、幼馴染で商業学校時代も親しかった野村商店(野村證券の前身)の野村新之助らは、株価を下落させるため栄之助に売り方に転じてもらうよう懇願。栄之助は長考の末、「父の代からお世話になっている皆さんへの恩返し」として翌日から大量の売りに出て、持ち株を売り切った後もカラ売りで抗戦した。これにより相場が急変すると読んだ大株主や相場師が一転して売り方に変り大暴落。大阪の仲買人らは九死に一生を得て逆に巨万の利益を手にすることとなり、「栄之助さんには足を向けて寝られない」と言わしめた。
☆アメリカで社会貢献に目覚める
「学問せなあかん」を口癖にしていた栄之助は、私財で夜学の塾を作っている。同時に関心を持ったのが、株で稼いだ利益を社会貢献に供することだった。明治42年、かの渋沢栄一を団
長とする渡米実業団に33才の若さで選ばれ、アメリカの公共施設などを視察。大実業家が私財を投じて建てたカーネギーホールなど、富豪が公共・慈善事業に寄付する文化に感動を覚える。
視察途上で父の死去を知った栄之助は、帰国後に供養も兼ねて100万円(現在の価値に換算して数十億円) の寄付を大阪市に申し出た。使い道について渋沢らと相談した栄之助は、公会堂の建設に決定。ちなみに定礎式に渋沢が出席し、「定礎」の字を揮毫している。
☆待たで散りゆく紅葉かな
この頃、大阪電燈(関西電力の前身のひとつ)の常務となっていた栄之助は、第一次世界大戦の影響で株式市場が恐慌状態となったことから岩本商店が傾きかけたため、職を辞して家業に戻った。「講和が結ばれれば株は暴落する」と見て売り方に回った栄之助であったが、大戦景気が来て買いが殺到し暴騰が続き莫大な損失を出す。周囲が大阪市への寄付を返してもらうように助言するものの、「一度寄付したものを返せというのは大阪商人の恥」と断った。
大正5年10月の日曜、栄之助は岩本商店の関係者ほぼ全員を京都へ松茸狩りに行かせ、自分は「気分がすぐれない」と店の2階にこもった。幾度かの外出後、店の隣の自宅で夕食をとってから奥の茶室に入り、しばらくして銃声が聞こえたため妻らが駆けつけると、陸軍時代のピストルでのどを打ち抜いた姿で発見された。まだ息のあった栄之助は建設中の公会堂から川を挟んだ場所にあった病院に運びこまれ、彼に助けられた株仲間が天満宮で夜通し火を焚いて祈願するも叶わず、5日後39才で死去。公会堂の完成を見ずにこの世を去った。自決の場にあった遺書には「全財産は債権者のために使い妻子には一文たりとも使うな・子孫は株式投資をしてはならない」などと記され、そばには次の辞世の句が残されていたという。『その秋をまたでちりゆく紅葉哉』
2年後の大正7年、公会堂が竣工。むろん落成式には栄之助の姿はなく遺影が正面に飾られた。そして大阪市長に公会堂の鍵箱を引き渡したのは、母のてるに付き添われた忘れ形見の4才
の善子であった。善子は、父親の後ろ姿を追うかのように、82才で他界するまで公会堂で嘱託として働き続けている。
国の重要文化財となった公会堂
☆ほぼ同じ位置にあった旧公会堂
大阪には明治期からすでに公会堂が存在しており、現在の中央公会堂の西側にあった。江戸時代に諸藩の蔵屋敷が立ち並んでいた中之島には、明治12年に京都から豊国神社(現在の公会堂の敷地は豊国神社の跡)が勧請され、のちに公園として整備が始まる。ここに建設された初代の公会堂は、明治36年に開催された第5回内国勧業博覧会関連の多人数の集会用として急造されたもので、木造2階建て漆喰塗の建物であった。そして新公会堂建設のため大正2年に博覧会の跡地の天王寺公園内に移設され、天王寺公会堂と称していたが、昭和11年の動物園拡張の際に老朽化で取り壊されている。
☆コンペにより決定された外観
栄之助の寄付をどのように使うかについて、当初は4つの案があった。その中から公会堂建設が選ばれた理由は、「どなたさまにも機嫌よく使ってもらうのがよろしい」という栄之助の母親の意見ともいわれている。寄付により設立された財団法人の建築顧問には、東京駅や日銀本店の設計で著名な辰野金吾が就任。設計原案は当時の一流建築士が参加するコンペで決定されることとなった。その結果、一等賞として採用されたのは最年少の岡田信一郎のネオ・ルネサンス様式のもので、それを元に辰野と大阪工業大学の創始者・片岡 安が実施設計を行っている。原案にバロック様式を加味して、主体の赤レンガに花崗岩などで装飾が施された地下1階・地上3階建ての外観は、堂々としていながら重過ぎず親しみやすさがあり市民の公会堂にふさわしいといわれ、落成後の一般公開には3日間で10万人以上が訪れたという記録がある。
また、南北の出入口には特色のあるキャノピー(庇)が取り付けられている。これは栄之助が「雨天時に訪れる人のために」と付けさせたもので、人柄を偲ばせるエピソードとして伝わっている。
☆壮麗かつモダンで見応えある内装
内装には、ネオ・ルネサンスを基調として幅広いデザインが取り入れられた。内部には大・中・小の集会室と10の会議室があり、それら以外の食堂・エントランス・階段などにも装飾が施されている。加えてシャンデリアやステンドグラス・家具調度類にも特色が多く、見ていて飽きない。
さらに洋風のデザインに和風の意匠や要素も加味されている。特筆すべきは3階の特別室で、天井や壁に日本書紀をモチーフとした神話のシーンや難波宮ゆかりの仁徳天皇像などが、明治期の洋画界の重鎮・松岡 壽によって描かれ、貴賓室として使われていた雰囲気が強く感じられる。
2階席もある大集会室では、過去にはロシアやイタリアの歌劇団の公演、アインシュタインやヘレン・ケラーの講演会など、大きなイベントが開催された。昨今は各種集会・講演会・演奏会などで使用され、3階の小・中集会室は結婚式や披露宴にも使われていて、施設利用の予約がとりづらい状況となっている。また、地下にはレストランと資料展示室があり、こちらは誰でも自由に利用・見学ができる。
☆保全・改修工事と重要文化財の指定
完成当時は荘厳な大建築であったが、近年は地震への耐久性や経年劣化が指摘されてきた。一時は市役所を含めた中之島再開発計画のなかで解体の議論も活発化。しかし「歴史的建造物の破壊は中之島の景観を損なう」という意見も多く、保存運動が展開される。昭和63年、大阪市は市民の要望に応えて永久保存を決定。再生資金として朝日新聞の呼びかけにより7億円もの寄付が市民・企業から集まっている。そして、防災上の安全性の強化や空調・音響・舞台装置の充実に、スロープなどのユニバーサルデザインの整備が加えられた保全工事が、平成11年から始まった。なお、これには過去の改修で損なわれた装飾などの復元も盛り込まれている。
その一例として、創建時には正面屋上にあったものの太平洋戦争による金属類供出で失われていたローマ神話の女神・ミネルバと商業の神・メルクリウス(メルキュール)の像が復活した。
平成14年に3年半をかけた工事が完了。美しい外観と内部意匠が歴史的に極めて重要と認められ、平成19年に公会堂建築として西日本初の国の重要文化財に指定された。




同窓会設立110周年という節目の年の総会・懇親会は、公会堂を全館貸し切りにしての開催となりました。大阪フロンティアバンドのファミリーコンサートとの同日開催ですので、大ホールで
の音楽鑑賞と公会堂の内部や資料室の見学ができます。歴史あるすばらしい建築物と天商生の大先輩、岩本栄之助に思いを馳せて、ぜひご参加ください。
※この記事は以下の文献等を参考に一部を引用して作成しました。
・大山勝男著 「義侠の相場師・岩本栄之助伝」
・山形政昭著 「大阪市中央公会堂の建築」
・大阪中之島公会堂 公式ホームページ

※大阪市中央公会堂 公式プロモーションビデオ(YouTube)